測定しておきたい水質チェック項目ランキング

アクアリウムで測定しておきたい水質チェック項目ランキングを具体的な数値と合わせて水槽管理に役立つ内容を紹介します。初心者の方にもわかりやすく簡単に紹介します。ランキングは2008年からアクアリウムの水質を測定し、記録し続けた経験を元に重要性が高いと感じたランキングになります。
1.水草水槽で測っておきたいランキング
水草水槽で測定したいランキング1位~9位の紹介です。
1.水草の育てやすさ・KH
炭酸塩硬度KHを測定することで水草の育てやすい水質を確認することができます。水草の好む水質は炭酸塩硬度KHの値が0~1°dHの値です。2°dH以上を超えると軟水を好む水草に成長不良が見られる場合があります。またソイルが劣化したり、レイアウトの石や水換えの水道水により硬度が高くなる場合は炭酸塩硬度KHの値が2°dH以上になりやすいです。おすすめの炭酸塩硬度KHの測定方法はこちらの記事をご覧ください。

2.酸性度・PH
水草水槽の場合PHを測定することで水草が好む水質を確認することができます。水草水槽の場合はPH6.5~7.0が育成しやすい値です。さらにKHとPHから水草に必要なCO2量の目安が把握できます。また水槽立ち上げ時はソイルからでる栄養分の硝酸塩でPHが下がりやすくなります。PHが6.3以下になるような水槽の場合は水換えによって栄養分を除去してPHを6.3以上に上げる必要があります。おすすめの酸性度・PHの測定方法はこちらの記事をご覧ください。
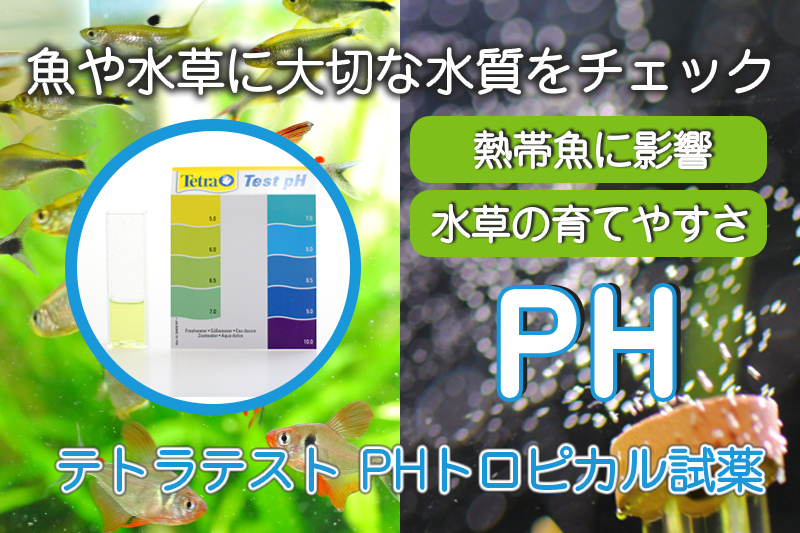
3.不純物量・TDS
水中の伝導率TDSを測定することで水槽内の不純物の量により水草の育てやすい傾向をチェックできます。TDSは水中内の溶けている物質量を数値化したものです。
水草育成の障害になるミネラル分(カルシウムやマグネシウム)の量をTDSを測定することで確認することができます。TDSが高い(※90ppm以上)場合はミネラル分(硬度)が高く水草育成には不向きな場合が多いです。※水槽立ち上げ時など水が濁っているなど不純物が多い場合はTDSは高くなるので、直接水道水を測ることでミネラル分(硬度)の目安が把握できます。また水換えが少ないコケが発生しやすい水槽はTDSが高くなる傾向があります。水道水と飼育水のTDSの値を比較して水槽内の不純物の蓄積(水道水-飼育水=汚れ量)が把握できます。おすすめの不純物量・TDSの測定方法はこちらの記事をご覧ください。

4.栄養分量・NO3
硝酸NO3はソイルや餌から発生する栄養分でコケの発生に影響します。硝酸塩を低く維持するために、水換えによって硝酸NO3の値を下げる必要があります。水草水槽では硝酸塩の値は1ppm以下になるように水換えを管理したいです。おすすめの栄養分量・NO3の測定方法はこちらの記事をご覧ください。
.jpg)
5.栄養分量・PO4
リン酸PO4は餌から溶け出し、水草やコケの栄養分として吸収されます。リン酸PO4が水槽内に蓄積するとガラス面に薄い緑のコケが発生します。リン酸PO4を低く維持するために、水換えによってリン酸PO4の値を下げる必要があります。水草水槽ではリン酸PO4の値は0.1ppm以下になるように水換えを管理したいです。おすすめの栄養分量・PO4の測定方法はこちらの記事をご覧ください。
.jpg)
6.毒性量・NH4
アンモニアNH4はバクテリアの活動が少ない水槽の立ち上げ時にソイルや熱帯魚の糞から発生します。アンモニアは毒性が高く検出されるような水槽では生体の飼育は危険です。水槽を立ち上げの水が濁った状態ではアンモニアが検出され濁りが消えた頃にアンモニアが消えていることがあります。アンモニアは0ppmにすることが重要です。おすすめの毒性量・NH4の測定方法はこちらの記事をご覧ください。
.jpg)
7.バクテリアの活動・NO2
亜硝酸NO2は毒性の強いアンモニアがバクテリアに分解された際に発生するため、バクテリアの発生を確認するためにチェックすることが多いです。(硝化サイクルの確認)水草水槽ではソイルから水槽立ち上げから1~2週間で発生しやすく、10日すぎるとバクテリアによって分解され検出されなくなることが多いです。亜硝酸NO2は毒性は弱いですが水槽内では検出されない0ppmにすることが重要です。おすすめのNO2の測定方法はこちらの記事をご覧ください。
.jpg)
8.栄養分量・K
カリウムKは水草に必要な栄養素のひとつです。カリウムKはアクアリウムでは基本的に測定する機会はないです。カリウムは※水道水や餌に含まれています。※水道水は0.5~2ppm程度のカリウムを含む地域が多いようです。カリウム液肥を添加をした場合に水草の量が少なかったり、毎日の餌の量によってカリウムが蓄積しまうおそれがあります。カリウム液肥を添加する場合はカリウム測定により過剰になりすぎないように確認することができます。私はカリウムは1ppm~4ppm以下になるように調整しています。おすすめの栄養分量・Kの測定方法はこちらの記事をご覧ください。

9.微量元素・Fe
鉄Feは水草に必要な微量元素のひとつです。水草水槽では一般的には鉄分を測定する機会は少ないです。私の経験では高くても0.05ppm~0.1ppm以下で十分だと感じます。0.5ppm以上になると生体にも水草にも有害とされています。水道水の鉄Feの基準値は0.3ppm以下です。水道管が錆びているなど鉄が溶け出した場合は水道水が赤くなることがあるそうです。鉄分主体の液肥を入れる場合、水槽の鉄分が過剰に蓄積しないためにも測定をおすすめします。おすすめの微量元素・Feの測定方法はこちらの記事をご覧ください。
.jpg)
2.熱帯魚水槽で測っておきたいランキング
熱帯魚水槽で測定したいランキング1位~5位の紹介です。
1.不純物量・TDS
TDSを測定することで水槽内の汚れ具合をチェックできます。TDSは水中内の溶けている物質を数値化したものです。水道水のTDSの値が高い場合は硬度が高くアルカリ性になりやすく、逆にTDSの値が低い場合は軟水になり弱酸性に傾きやすいです。また水換えが少ないコケが発生しやすい水槽はTDSが高くなる傾向があります。水道水と飼育水のTDSの値を比較して水槽内の不純物の蓄積(水道水-飼育水=汚れ量)が把握できます。おすすめの不純物量・TDSの測定方法はこちらの記事をご覧ください。

2.酸性度・PH
熱帯魚水槽の場合PHを測定することで熱帯魚の好む水質の傾向がわかります。軟水を好む魚はPH6.0~7.0(弱酸性)、硬水を好む魚はPH7.0~8.5(弱アルカリ性)を好む傾向があります。また魚が多くいて栄養分が溜まりやすい水槽は、硝酸塩NO3の影響でPHが下がりやすくなります。PHが6.5以下になるような水槽の場合は水換えによって栄養分を除去する必要があります。おすすめの酸性度・PHの測定方法はこちらの記事をご覧ください。
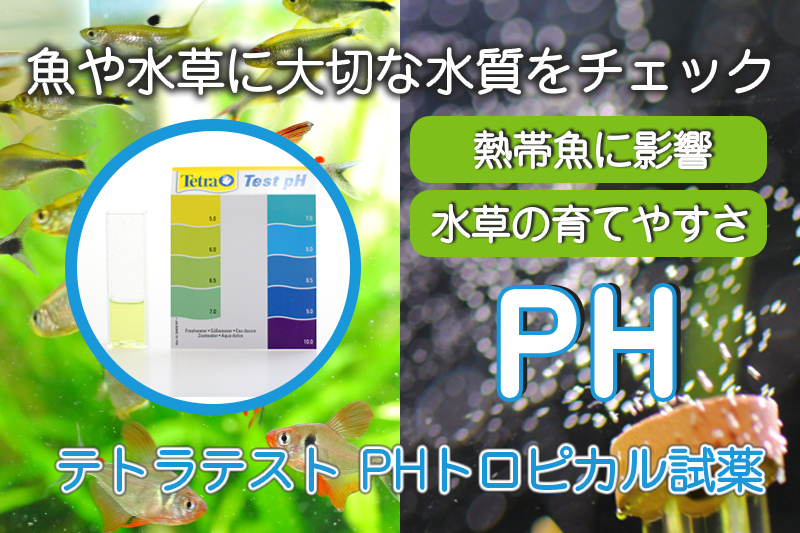
3.栄養分量・NO3
硝酸NO3はソイルや餌から発生する栄養分でコケの発生に影響がでます。硝酸塩を低く維持するために、水換えによって硝酸NO3の値を下げる必要があります。水草が少ない魚が多い水槽では25ppm以上になる場合がありますが、魚の病気を抑えるためには5ppm以下が理想です。おすすめの栄養分量・NO3の測定方法はこちらの記事をご覧ください。
.jpg)
4.毒性量・NH4
アンモニアNH4はバクテリアが少ない水槽の立ち上げ時にソイルや熱帯魚の糞から発生します。水槽立ち上げ初期ではアンモニアが発生しやすく飼育数は少なくアンモニアが蓄積しづらい管理が重要になります。水槽初期の水が濁った状態ではアンモニアが検出される場合があり、濁りが消えた頃にアンモニアが消えていることがあります。アンモニアは0ppmにすることが重要です。おすすめの毒性量・NH4の測定方法はこちらの記事をご覧ください。
.jpg)
5.バクテリアの活動・NO2
亜硝酸NO2は毒性の強いアンモニアがバクテリアに分解された際に発生する物質なため、バクテリアの発生を確認するためにチェックすることが多いです。熱帯魚水槽では瀘過器にバクテリアが定着する前に魚を入れると発生しやすいです。飼育環境にもよりますがソイルを使った水槽の場合は、水槽立ち上げから10日すぎるとバクテリアによって分解され亜硝酸NO2は検出されなくなることが多いです。亜硝酸NO2は毒性は弱いですが水槽内では検出されない0ppmにすることが重要です。おすすめのNO2の測定方法はこちらの記事をご覧ください。
.jpg)
全硬度(GH・TH)について
今回GHの測定は除外しています。理由としてはアクアリウム製のGHの測定が難しく感じたからです。テトラテスト 総硬度試薬GH テストもリニューアルされ改善されたりしていました。しかしその後、理由はわかりませんがテトラのGHは廃盤になってしまいました。硬度の測定は、共立理化学研究所製のパックテスト 全硬度 THがありますが、50回分(5,000円)と高くアクアリウム用としては、気軽に購入できないこともあり、今回はランキングから外しています。ただし共立理化学研究所製のパックテストはADAから5回分(1,000円)は販売されているので、近くに特約店があれば購入可能です。またGH・THをランキングに加えなかった理由は、KH(炭酸塩硬度)やTDSの測定により、簡単に硬度の目安・影響が把握できる為です。



水草が育たない・枯れる原因など綺麗な水草水槽づくりに役立つ記事6選
-1-150x150.jpg)
-150x150.jpg)










ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません